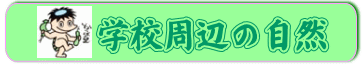|
|
| 35号 |
牛久自然観察の森
<春が来た! ~ウメの花が咲いています>
|
2014年 3月23日発行 |
 |
| 顔をつっこんで、ウメの花みつを吸うニホンミツバチ。他のハナバチ類はまだ、ほとんど活動しない。 |
|
| 34号 |
牛久二小
<冬の生きもの観察 植物の冬ごし ~冬に咲く花とコケのなかま>
|
2014年 3月10日発行 |
 |
| とても寒そうな中、日ざしを受けて花を咲かせるサザンカ(左)、オオイヌノフグリ(右) |
|
| 33号 |
牛久二小
<冬の生きもの観察 植物の冬ごし ~なかまをふやす、タネまきのしかた>
|
2014年 3月10日発行 |
 |
| フックで動物の毛皮にひっついてタネが運ばれるオオオナモミ。マジックテープは、このしくみをヒントに発明された |
|
| 32号 |
牛久二小
<冬の生きもの観察 植物の冬ごし ~冬芽とロゼット>
|
2014年 3月 2日発行 |
 |
| タンポポ(左上)、ブタナ(右上)、オニノゲシ(左下)、タネツケバナ(右下)の「ロゼット」。このような姿をしていると、お日さまの光をたくさん受けられるし、冷たい風をまともに受けなくてすむ。 |
|
| 31号 |
牛久二小
<冬の生きもの観察 動物の冬ごし>
|
2014年 2月 9日発行 |
 |
| サクラの幹で集団で冬ごししていたヨコヅナサシガメの幼虫 |
|
| 30号 |
牛久二小
< 冬の生きもの観察速報(かんさつそくほう) テントウムシの卵を見つけたよ!! >
|
2014年 1月23日発行 |
 |
| 石の裏にあったテントウムシの卵(左)とその拡大(かくだい)(中)。土にも(右) |
|
| 29号 |
牛久二小
< 秋の生きもの観察 ⑦紅葉(こうよう) >
|
2014年 1月23日発行 |
 |
| まっ赤に紅葉したニシキギ(上2枚)。日ざしを受けてまぶしいくらい。カキの葉も、黄色に色づいていました(左)。 |
|
| 28号 |
牛久二小
< 秋の生きもの観察 ⑥秋(~冬)に咲く花 >
|
2014年 1月23日発行 |
 |
| 秋から冬にかけて咲くシロダモ(左)とヤツデ(右)。ハチはもうほとんど見られず、ハエやハナアブが多く訪れる |
|
| 27号 |
牛久二小
< 秋の生きもの観察 ⑤その他の昆虫,クモ >
|
2013年12月 5日発行 |
 |
 |
虫が集団で越冬する、ヨコヅナサシガメ。
アオマツムシを捕え、体液を吸う(左)。幹の割れ目に集まり始める(右)。 |
|
| 26号 |
牛久二小
< 秋の生きもの観察 ④バッタ,カマキリ >
|
2013年12月 4日発行 |
 |
| オンブバッタ(左)とエンマコオロギ(右)。これら、ほとんどのバッタの仲間は卵で冬を越す |
|
| 25号 |
牛久二小
< 秋の生きもの観察 ③ハチ >
|
2013年12月 3日発行 |
 |
| キンケハラナガツチバチのオス。セイタカアワダチソウの花みつを吸う(左)。クレオメのみつを吸う(右)。 |
|
| 24号 |
牛久二小
< 秋の生きもの観察 ②トンボ >
|
2013年11月11日発行 |
 |
| アキアカネのオス(左)とナツアカネのオス(右)。胸のもようや、赤くなる部分がちがう |
|
| 23号 |
牛久二小
< 秋の生きもの観察 ①チョウ >
|
2013年11月 9日発行 |
 |
| はねを休めるヤマトシジミのオス。幼虫で冬を越す。幼虫のえさはカタバミの葉 |
|
| 22号 |
牛久二小
< 夏の終わりの生きもの観察 ②動物 > |
2013年 9月26日発行 |
 |
| ショウリョウバッタの緑色型(左)と褐色型(右)。どちらも、はねがのびた成虫 |
|
| 21号 |
ひたち野西近隣公園
< 速報 夏の終わりのみずべ公園 > |
2013年 9月20日発行 |
 |
| つながりながら産卵するギンヤンマ。前がオスで後ろがメス |
|
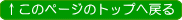 |
| 20号 |
牛久二小
< 夏の終わりの生きもの観察 ①植物 > |
2013年 9月16日発行 |
 |
| 黄色の花をさかんに咲(さ)かせるラッカセイ(左)と、校舎(こうしゃ)にかけられたネットに咲くヘチマ(右)。 |
|
| 19号 |
牛久二小
< 夏の校庭で生きもの観察 ③その他 > |
2013年 9月14日発行 |
 |
| 白と黒のパンダもようと、長い口先、長くてがっしりした前あしが特ちょうのオジロアシナガゾウムシ |
|
| 18号 |
牛久二小
< 夏の校庭で生きもの観察 ②バッタ,カマキリ > |
2013年 9月 5日発行 |
 |
| クルマバッタの幼虫(ようちゅう)。褐色(かっしょく)のものと緑色のものがいる |
|
| 17号 |
牛久二小
< 夏の校庭で生きもの観察 ①花と昆虫 > |
2013年 9月 3日発行 |
 |
| ガクアジサイ(左)と、その花粉を食べるヒラタアブのなかま(右)。ハチに似ているが、ハエに近いなかま。 |
|
| 16号 |
ひたち野うしく小
< 夏の動物観察 ~みずべ公園 ⑦その他 > |
2013年 8月30日発行 |
 |

 |

 |
| 茨城県では珍(めずら)しいブチヒゲカメムシ |
細身(ほそみ)のホソヘリカメムシ:右 |
|
| 15号 |
ひたち野うしく小
< 夏の動物観察 ~みずべ公園 ⑥クモ > |
2013年 8月24日発行 |
 |
| 左からササグモ、メガネドヨウグモ、ドヨウオニグモ。嫌いな人が多いクモですが、作物の害虫を食べてくれます。 |
|
| 14号 |
ひたち野うしく小
< 夏の動物観察 ~みずべ公園 ⑤甲虫類 > |
2013年 8月23日発行 |
 |
| いろいろな植物の葉や花を食べるマメコガネ |
|
| 13号 |
ひたち野うしく小
< 夏の動物観察 ~みずべ公園 ④とんぼ > |
2013年 8月16日発行 |
 |
 |
| 枯(か)れ草の茎(くき)で休む、コシアキトンボのオス。 |
オタマジャクシの池で、他のトンボとなわばり争いをする姿がよく見かけられる、シオカラトンボのオス。 |
|
| 12号 |
ひたち野うしく小
< 夏の動物観察 ~みずべ公園 ③バッタの仲間 > |
2013年 7月22日発行 |
 |
 |
| トノサマバッタの幼虫 |
キリギリスのなかま?の幼虫。
腹部(ふくぶ)のせなか側に、こぶのようなものがある |
|
| 11号 |
ひたち野うしく小
< 夏の動物観察 ~みずべ公園 ②ハチやアリの仲間 > |
2013年 7月 6日発行 |
 |
| ブタナのみつを吸うセイヨウミツバチ(左上)。アカツメクサのみつを吸うセイヨウミツバチ(右) |
|
| 10号 |
ひたち野うしく小
< 夏の動物観察 ~みずべ公園 ①チョウやガの仲間 > |
2013年 7月 3日発行 |
 |
| チョウの仲間では一番多く見られたベニシジミと,その上を通るヒメハナバチの仲間(左).どちらもヒメジョオンのみつを吸っていました.右はよく似たハルジオンの花でみつを吸うベニシジミと,ミナミヒメヒラタアブ.アリもいますね. |
|
| 09号 |
ひたち野うしく小
< 春の生きもの観察 ~みずべ公園 ⑤その他の動物 > |
2013年 6月17日発行 |
 |
| 土をつついてエサを探すハクセキレイ(左)と,ムクドリ(中、虫をくわえた),キジバト(右)。 |
|
| 08号 |
ひたち野うしく小
< 春の生きもの観察 ~みずべ公園 ④草花に来る昆虫たち > |
2013年 6月 6日発行 |
 |
| ハルジオンのみつを吸うベニシジミ(左)と、花粉(かふん)を食べるコアオハナムグリ(右)。 |
|
| 07号 |
ひたち野うしく小
< 春の生きもの観察 ~みずべ公園 ③その他の樹木と昆虫たち > |
2013年 5月30日発行 |
 |
| 高い枝についていたハラビロカマキリの卵のう(左)と、皆さんの身長より低い木の枝についていたオオカマキリの卵のう(右)。卵のうをつくる場所に違いがあるのは、生活場所に少しずれがあるためか? |
|
| 06号 |
ひたち野うしく小
< 春の生きもの観察 ~みずべ公園 ②クサギに集まる昆虫たち > |
2013年 5月27日発行 |
 |
| 交尾(こうび)中のナミテントウ(左)や、産卵(さんらん)中のも(右)見つけましたね。 黒地に赤い星2つが多かったですね |
 |
| 同じナミテントウでも、もようはいろいろ。赤地に黒い星19個(左)とか黄色1色もいました。脱皮中の幼虫も(右) |
|
| 05号 |
牛久市、稲敷市、龍ヶ崎市
< 竹の秋と椎(しい)の春,花粉の運び手とめしべのつくり> |
2013年 5月25日発行 |
| 「竹の秋」ということばをご存じですか?俳句(はいく)の春の季語(きご)ですが、少し前から竹の葉が写真のように黄色~オレンジ色に紅葉しています。春に紅葉?と不思議に思うかもしれませんが、竹の仲間はタケノコを伸ばしたあと5月から6月にかけて葉を落とし、新しい葉がかわってのびてきます。 |
| 「写真」?・・・は、左の 05号 をクリックして本文(4ページ)をご覧下さい |
|
| 04号 |
ひたち野うしく小
< 春の生きもの観察 ~みずべ公園 ①エゴノキの花に集まる昆虫たち > |
2013年 5月22日発行 |
 |
| 蜜(みつ)を吸い、花粉を集めて、後ろあしに「花粉団子(だんご)」が目だつコマルハナバチのメス。 |
|
| 03号 |
牛久二小
< 春の生きもの観察 ~4年生と校庭を歩く ③昆虫 > |
2013年 5月11日発行 |
 |
| ハチそっくりでみつや花粉を食べるナミハナアブ。はね2枚、触角が短く複眼が大きいことなどからハチと区別できる |
|
| 02号 |
牛久二小
< 春の生きもの観察 ~4年生と校庭を歩く ②植物-樹木 > |
2013年 5月 8日発行 |
 |
| バラ科の仲間、サトザクラ(左)とコデマリ(右)。サトザクラのたくさんの花弁は、雄しべが変化したもの。 |
|
| 01号 |
牛久二小
< 春の生きもの観察 ~4年生と校庭を歩く ①植物-草 > |
2013年 5月 4日発行 |
 |
| 花が赤紫で目だつカラスノエンドウ(左)と、白い小さな花が集まってかたまりをつくるシロツメクサ(右)。どちらもマメ科の仲間で、花が終わると「豆」ができる。 |
|